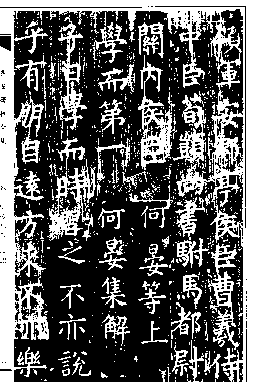

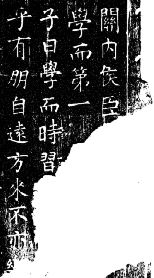
図A 「西安碑林全集」181 p.7
図B 東京大学総合図書館蔵拓本(部分)
図C 京都大学人文科学研究所蔵拓本(部分)
西安碑林の「開成石経」(かいせいせきけい)は、 唐開成二年(837)勅命によって石に刻まれた儒教経典(けいてん)の一大集成で、 経典の本文、それを表現する字体の両方を、一気に規範として制定し、 その影響は、後の宋版、更には現代日本の活字字体にまで及んでいます。
その全貌は高峽編 「西安碑林全集」(中国廣東経済出版社・海天出版社共同出版) 全15帙、 200冊(1999年)として公刊され、容易に見られるようになりました。
ところが、「西安碑林全集」を見ていくと、 中にはどうしても開成石経が規範として定めた字体とは思われないような字も散見されます。 これは何故なのでしょうか。
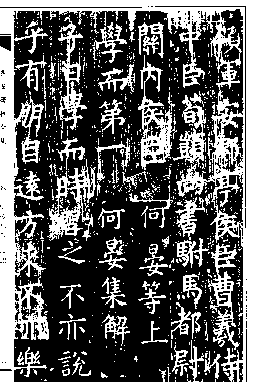
|

|
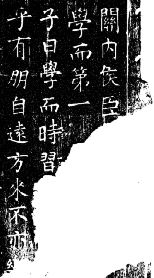
|
|
図A 「西安碑林全集」181 p.7 |
図B 東京大学総合図書館蔵拓本(部分) |
図C 京都大学人文科学研究所蔵拓本(部分) |
左から「西安碑林全集」、商品としての拓本複製(清時代?)、原石の拓本です。
御覧のように、商品としての拓本複製には、原石に欠けている部分が補われています。 これは、明・万暦十六(1588)に行なわれた補刻で、 原石では別の石を立て、そこにまとめてあるのですが、 商品としての拓本複製の中には、 この補刻部分を丁寧に切り取って、欠けた部分に貼り付けたものが存在します。 上記の東京大学総合図書館蔵本はその例で、 「補缺」として切り取る前のままの形で残された拓本複製も(東洋文庫などに)現存しています。 「西安碑林全集」は、実は原石そのものではなく、 こうした「補刻を貼り付けて補った」拓本を複製したものであり、 その字体が全て開成二年に遡るものとは言えないのです。
原石から採集した拓本・所蔵元が公刊した複製といえども、
その本来の姿を伝えているとは限らない、これが現実です。
GICAS では、既に拓本が存在するものであっても、
敢えて現地に赴いて碑文の現物を調査し鮮明に撮影する事に努力しましたが、
それにはこうした理由もあるのです。